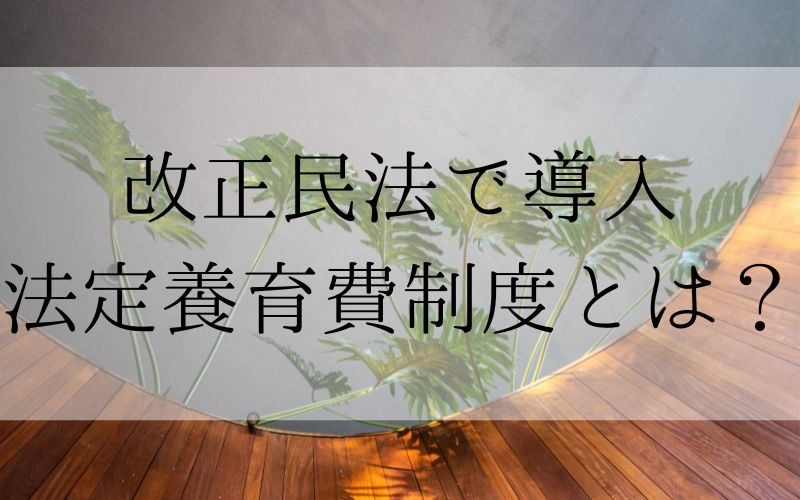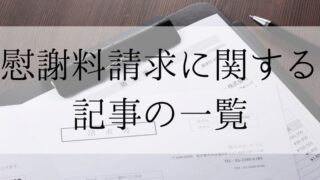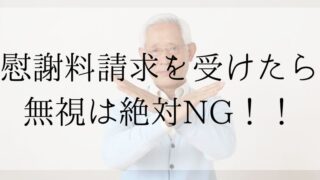「離婚したら養育費はちゃんともらえるの?」そう不安に感じる方は少なくありません。実際、厚生労働省の2021年度調査によると、母子世帯で養育費の取り決めをしているのはわずか約47%、実際に受給しているのは約28%にとどまっています。この深刻な状況を改善するため、2026年5月までに新たな「法定養育費」制度が導入されます。
新しい制度は、養育費を確実に受け取るための心強い味方になってくれるはずです。
なお、この記事の出典は、法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」を参照して作成しております。
養育費不払いをなくす「法定養育費制度」とは?
養育費不払いをなくす新制度とは
法定養育費制度は、養育費の取り決めがない場合でも、法律に基づいて一定額を請求できる仕組みです。これまでの制度では、養育費の支払いを受けるには、まず父母の協議や裁判所の手続きを通じて金額を決める必要がありました。しかし、この新制度では、そうした手続きを経なくても請求が可能になります。
制度の大きなポイントとしては、まず、「法定養育費の請求権が新設」されるということです。これにより、離婚時に養育費を決めていなくても、一定額を請求する権利が生まれるため、離婚協議が長期化することを防ぐなどの効果がかんがえられます。
また、養育費債権に「先取特権」が付与されることも特徴です。「先取特権(さきどりとっけん)」とは、一言でいうと「他の誰よりも先に、お金をもらう権利」のことです。養育費に先取特権が付くと、あなたは他の債権者よりも優先的に、元配偶者の財産から養育費を受け取ることができます。これは、子どもの生活を保障するという社会的に重要な理由から、法律によって特別に認められる権利なのです。
この改正により、養育費の取り決め文書があれば、公正証書などの「債務名義」がなくても、強制執行の手続きを申し立てることが可能になります。
これまでの制度との違いは?
これまで、養育費は「話し合って決めるもの」でした。しかし、もし相手が話し合いに応じてくれないと、養育費の調停や審判を申し立てなければならず、請求することすら難しいのが現実だったのです。冒頭でも述べた通り、母子世帯で養育費の取り決めをしているのはわずか約47%、実際に受給しているのは約28%にとどまっていますが、それは手続きの複雑さが一因であったという面は否めません。
しかし、今回の改正によって、こうした状況は変わります。なぜなら、養育費の支払い義務が「離婚の日から発生する」と法律で明確に定められるからです。これは、養育費をめぐる大きな一歩と言えるでしょう。
たとえば、離婚後に相手と連絡が取れなくなってしまっても、法律上の根拠をもって養育費を請求できるのです。具体的には、支払う義務を負う親は、毎月末にその月の分の養育費を支払う必要があります。
では、この養育費はいつまで発生し続けるのでしょうか。この点も法律で具体的に定められています。養育費の支払いは、次のいずれか早い日まで続きます。
- 父母が養育費の取り決めをしたとき
- 家庭裁判所における養育費の審判が確定したとき
- 子どもが18歳に達したとき
ただし、注意すべき点があります。この新しい法律は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されるのです。もし施行前に離婚していた場合は、従来通り、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きで養育費の額を取り決める必要があります。
法定養育費制度では、養育費はいくらもらえる?
法務省がまとめた省令案では、子ども一人あたり月額2万円
「法定養育費」が具体的にいくらになるのか、最も気になるところでしょう。NHKの報道によると、法務省がまとめた省令案では、子ども一人あたり月額2万円とすることが柱になっています。
この金額は、法務省が子どもの「最低限度の生活を維持するのに必要な標準的な費用」として設定したものです。ただし、この金額はあくまで目安であり、離婚後の親の収入や資産、子どもの生活状況に応じて、個別に養育費の額を決めることが前提になっています。
つまり、月額2万円という金額は、話し合いが困難な場合に子どもの生活を保障するための「セーフティネット」として機能するものです。この金額は、最終的にパブリックコメント(国民の意見募集)を経て決定されます。(出典:NHK「『法定養育費』月額2万円とする省令案まとめる 法務省」)
強制執行で上限8万円?
養育費の支払いが滞った場合、相手の財産を差し押さえて養育費を回収する強制執行という手続きが取れます。法定養育費制度では、この手続きがより円滑に進むようになります。
具体的には、法定養育費の支払いが滞った場合、相手の財産を差し押さえ、子ども1人あたり月額8万円を上限として優先的に弁済を受けることができます。
また、相手の財産が不明な場合でも、「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」が債務名義なしで利用できるようになり、養育費の回収がしやすくなります。
養育費は今後どうなる?
自分たちで決めた方が良い、という現実は変わらない
新しい法定養育費制度は、養育費の取り決めが難しいケースで、あなたの生活を支えてくれる心強い制度です。しかし、実はこれだけでは子どもの将来には十分ではないかもしれません。
なぜなら、月額2万円は、あくまで子どもの最低限の生活を維持するための金額だからです。もし、お子さんが塾や習い事、大学進学を望む場合、この金額だけでは足りなくなってしまうことがほとんどです。
ですから、やはり離婚時に夫婦で話し合い、より具体的な養育費の額を決めることがとても大切なのです。
養育費の不払いで弁護士に相談すべき
1. 相手との交渉をすべて任せられる
相手と直接交渉するのは、精神的に大きな負担です。過去の感情的な対立が再燃し、話し合いがこじれることもあります。
弁護士はあなたの代理人として、冷静かつ論理的に交渉を進めます。第三者である弁護士が介入することで、相手も真剣に話し合いに応じることが多くなります。
その結果、スムーズに解決へと向かうことができるのです。
2. 強制的に養育費を回収できる
話し合いで解決できない場合、最終的には法的な手段に訴える必要があります。弁護士は、相手の給与や銀行口座を差し押さえる「強制執行」の手続きを代行してくれます。
強制執行を行うには、調停調書や公正証書といった「債務名義」が必要です。これらの書類の作成も、弁護士がサポートしてくれます。
3. 養育費の適正額を算定できる
「養育費算定表」は、裁判所が示す養育費の目安です。しかし、これはあくまで目安にすぎません。
弁護士は、相手の正確な収入や資産状況を調査し、より適正な養育費を算定します。
過去の判例や個別の事情を踏まえることで、算定表以上の金額を勝ち取れる可能性も出てきます。これは、あなた自身では難しい専門的な作業です。