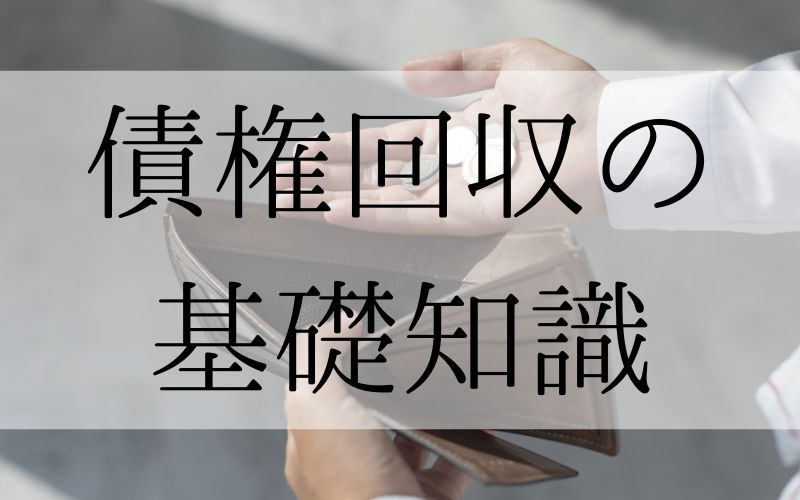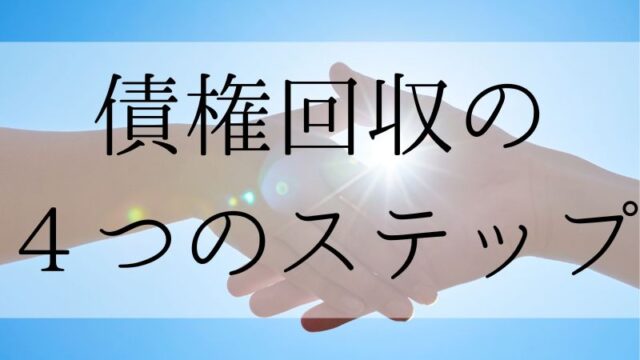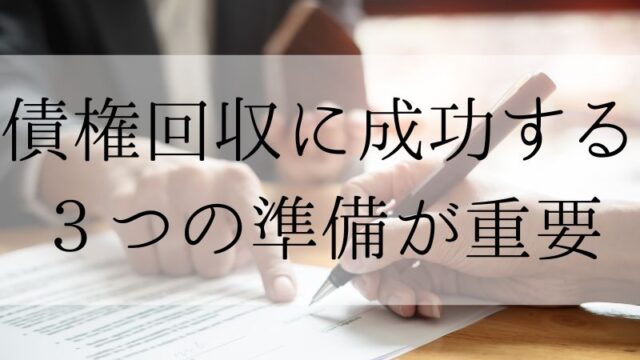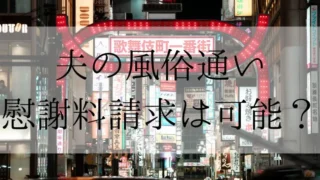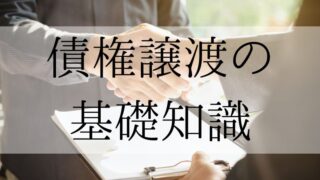「貸したお金が返ってこない」 「仕事の代金を払ってもらえない」
このようなトラブルに直面したとき、どうすればいいのか途方に暮れてしまう方も多いのではないでしょうか。実は、お金が戻ってこないというトラブルは決して他人事ではなく、最近では企業の倒産や個人の破産が増えているため、誰もが巻き込まれる可能性があるのです。だからこそ、正しい知識をもって、安全に債権回収を行う方法を知っておくことが大切です。
この記事では、債権回収の基本知識から、個人で行うことの危険性、そして専門家へ依頼するメリットまでを、わかりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたの抱えるお金の悩みを解決するヒントが見つかるはずです。
債権回収とは?知っておくべきキホン
債権回収とは?知っておくべき基本のキホン
「貸したお金がなかなか返ってこない」 「商品やサービスを提供したのに、代金を払ってもらえない」
このような状況に直面したとき、多くの人はまず、相手に電話をしたり、直接会って「返してほしい」とお願いしたりするかもしれません。また、家族や会社に告げ口をして、お金を代わりに払ってもらおうとする人もいるでしょう。
しかし、こうしたアプローチだけでは効果がない場合が多く、最悪のケースでは法律違反のトラブルに巻き込まれるリスクさえあります。
そこで重要になるのが、法律に基づいた「適法かつ効果的な債権回収」です。これは、単にお金を催促するだけでなく、法的な知識や手続きを使い、安全かつ確実に未払いの債権を回収する活動を指します。法的なリスクを避け、安全かつ確実に債権を回収するには、法律のプロである弁護士に相談し、適切な手続きを踏むことが最も賢明な方法なのです。
債権、債務とは?
債権回収とは、文字通り「未収債権を回収」するという活動です。では、債権、債務とは何でしょうか?
債権とは、特定の人が、別の人に対して、特定の行為を請求できる権利のことです。一方、債務とは、特定の人が、別の人に対して、特定の行為をしなければならない義務のことです。
例えば、あなたが友だちに1万円を貸したら、あなたは債権者、友だちは債務者になります。この債権を確実に回収することは、私たちの生活やビジネスを守る上で非常に大切な行動です。
なぜ債権回収はそんなに大事なのか?
実は、お金を返してもらえない、というトラブルは決して他人事ではありません。
日本全体の倒産件数は増加傾向にあります。株式会社帝国データバンクの調査によると、2024年の倒産件数が前年比15%増の1万6件となり、3年連続で増加していることを報じています。
この数字は、みなさんの取引先やお客様が、いつ倒産してもおかしくない状況であることを示しています。もし取引先が倒産すれば、未払いの売掛金(商品やサービスの代金)を回収できなくなるリスクが高まります。そうなると、会社のお金がなくなり、経営が苦しくなってしまいます。
さらに、個人の自己破産件数も増加傾向にあり、物価高や家計の圧迫が原因で支払いが滞るケースが増えています。ですから、倒産件数が増えている今、債権回収は自分の会社や生活を守るための、絶対に欠かせない行動なのです。
個人で債権回収、その危険性とリスク
「自分が貸したお金なんだから、どんな手を使ってもいいだろう」と考えてはいませんか?それは大きな間違いです。
個人で債権回収を行うことは、違法な取り立てによって犯罪者になるリスクがあるだけでなく、他人の債権を回収するとサービサー法や弁護士法に違反する可能性もあります。
サービサー法・弁護士法違反に注意
法務省の許可を得た「債権回収会社(サービサー)」でなければ、他人の債権を回収する業務はできません。サービサー法第33条には、許可なくこの業務を行った場合、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という重い罰則が定められています。
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。
また、弁護士法第72条では、弁護士ではない人が報酬を得て法律事務を行うことを禁止しています。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
債権回収は法律事務の一つです。報酬を受け取って他人の債権回収を代行すると、この法律に違反する可能性があるので注意が必要です。
債権回収が原因でトラブルに巻き込まれる
「貸したお金なんだから、どんな手を使ってもいいだろう」と考えてはいませんか?実は、その考えは非常に危険です。債権回収が原因でトラブルに巻き込まれるという現実があります。
たとえば、債務者に対して「家族にばらすぞ」「家に押し掛けるぞ」などと脅したり、暴言を吐いたりする行為は、脅迫罪や恐喝罪に問われる可能性があります。また、相手の家に無理やり入ろうとすれば、住居侵入罪になります。たとえ正当な権利があっても、方法を間違えれば、逆に自分が訴えられてしまうのです。
実際に起こった維持権を紹介しましょう。
2024年3月、福島市で借金の取り立てをしていた70代の男性が、債務者の男に鈍器で殴られ、意識不明の重体となる殺人未遂事件が起きました。男は裁判で起訴内容を認めています。この事例は、債権者を債務者が攻撃した結果起こったことであり、債権回収は一歩間違えれば凶悪な事件に発展する現実を示しています。(TBS NEWS DIG:借金返せず“紙片”入った茶封筒持って…借金回収の70代男性を殺害未遂の罪)
また、暴力団が債権回収に関わるケースも多く、その場合は暴力や脅迫が伴うことがほとんどです。
知人が暴力団員に債権回収を依頼した結果、依頼した知人自身も弁護士法違反や恐喝罪の共犯として逮捕された事例も存在します。
022年には、工藤会の幹部が、借金返済が滞った男性に対し「俺の仕事が何か知っているのか」などと暴力団の威力を示して返済を迫ったとして、暴力団対策法違反の罪で実刑判決を受けています。このように、債権回収という名目で、法律を無視した行為が行われる事例は後を絶ちません。(産経新聞:「俺の仕事知ってるか」工藤会幹部に実刑、借金返済迫る)
上記のように、債権回収はお金をめぐる問題であるため、感情的になりやすく、思わぬトラブルに発展するリスクを常に抱えているのです。
まとめ
債権回収はなぜ重要か?
債権回収は、自分の財産や会社の経営を守るための不可欠な活動です。最近では、企業の倒産件数や個人の自己破産が増加傾向にあり、誰にとっても他人事ではありません。株式会社帝国データバンクの調査によると、2024年の企業倒産件数は前年より15%増の1万6件に達し、3年連続で増え続けています。この背景には、物価高や人手不足といった厳しい経済状況があります。
もし取引先が倒産すれば、未払いの売掛金(商品やサービスの代金)は回収が難しくなります。また、個人の自己破産が増えている今、個人への貸付や家賃なども、回収できなくなる可能性が高まっています。
だからこそ、リスクを未然に防ぐためにも、日頃から債権回収への意識を高めておくことが大切なのです。
個人での債権回収は危険!法律を守って安全に
とはいえ、「自分でなんとかしよう」と考えるのは危険な場合があります。なぜなら、個人での債権回収は、思わぬトラブルや法律違反を招く可能性があるからです。
感情的に脅したり、無理やり返済を迫ったりする行為は、恐喝罪や強要罪といった刑事罰の対象になります。実際に、借金の取り立てが原因で殺人未遂事件に発展した悲しいニュースも報道されています。
さらに、他人の債権を報酬をもらって回収する行為は、サービサー法や弁護士法に違反する可能性があります。
安全かつ確実に債権を回収するには、法律のプロである弁護士に相談し、適切な手続きを踏むことが最も賢明な方法なのです。
記事の重要ワードと概念
今回の記事で特に重要なワードと概念を5つピックアップしました。
- 債権/債務
- サービサー法、弁護士法
- 違法な取り立て
理解度チェック
問題1:「債権」と「債務」の違いを、簡単な言葉で説明してください。
債権とは、お金を返してもらう「権利」のことです。一方、債務とは、お金を返す「義務」のことを指します。お金を貸した人が債権者、借りた人が債務者になります。
問題2:「サービサー法」とは、どのような目的で作られた法律ですか
回答2 サービサー法は、法務大臣の許可を得た「債権回収会社(サービサー)」だけが、他人の債権回収を代行できると定めた法律です。この法律は、暴力団などの反社会的勢力が債権回収に関わるのを防ぐ目的で作られました。
問題3:「弁護士法違反」に該当する可能性があるのは、どのような行為ですか?
回答3 弁護士ではない人が、報酬を得る目的で債権回収などの法律事務を行うことです。たとえば、「友人の借金を代わりに回収してくれたら報酬を払う」と頼まれて引き受けるような行為がこれにあたります。
問題4:個人で借金の取り立てを行った場合、どのような行為が「違法な取り立て」として罪に問われる可能性がありますか?2つ以上挙げてください。
違法な取り立てには、次のような行為が挙げられます。
住居侵入罪: 相手の許可なく自宅に押し入る行為。
脅迫罪・恐喝罪: 「家族にバラすぞ」「職場に押しかけるぞ」と脅す行為。
強要罪: 夜間に何度も電話をかけたり、無理やり返済を迫ったりする行為。