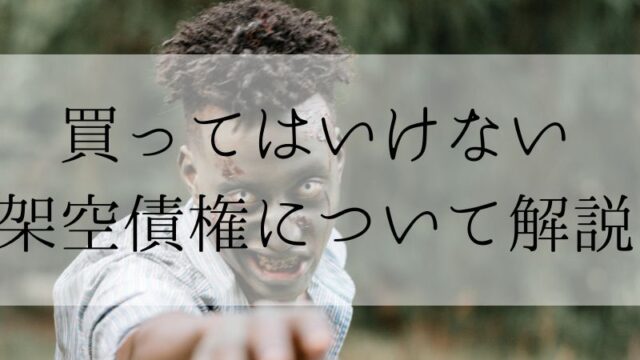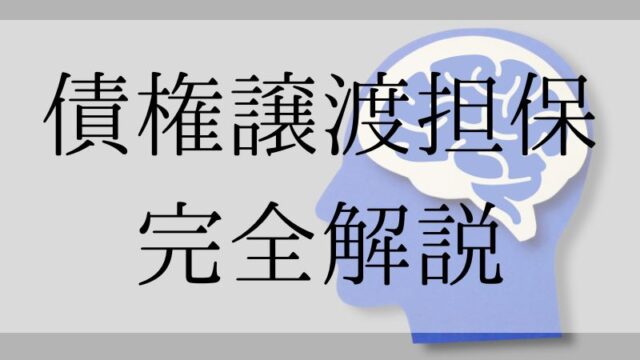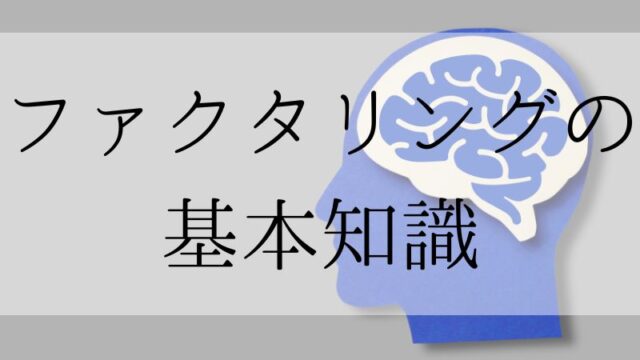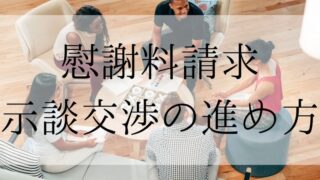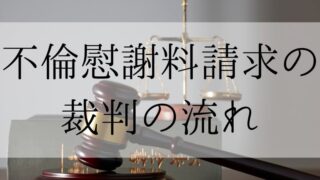「手元に売掛金があるけれど、入金まで待てない…」。事業を営んでいると、そんな資金繰りの悩みに直面することがありますよね。急な支払いや仕入れが必要になった時、銀行融資は審査に時間がかかり、間に合わないことも多いです。
そんな時、頼りになるのが「ファクタリング」です。ファクタリングは、あなたが持っている売掛金(請求書)を、支払い日よりも早く現金に変えることができるサービスです。つまり、売掛金の入金を待つ必要がなく、すぐに運転資金を確保できるのです。
「でも、ファクタリングって借金とはどう違うの?」「法律的には大丈夫なの?」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。実は、ファクタリングは日本の民法が定める「債権譲渡」というルールに基づいて成立しています。これは、お金を借りるのとは根本的に異なる取引なのです。
この記事では、ファクタリングが法的にどのように成り立っているのかを、難しい法律用語を使わずに分かりやすく解説します。ファクタリングを正しく理解し、安心して資金調達ができるようになるために、ぜひ最後までお読みください。
ファクタリングとは
ファクタリングは、企業が所有する売掛金を、支払い期日よりも早く現金に変える資金調達の手段です。これは、売掛金をファクタリング会社に売却することで実現します。
たとえば、あなたが製造業を営んでいて、大口の取引先に商品を納品したとしましょう。代金として100万円の請求書(売掛金)を発行しましたが、入金は2ヶ月後です。その間に、新しい商品の仕入れや従業員の給料を支払う必要があるとします。ここでファクタリングを利用すれば、入金日を待たずに、すぐに現金を手にすることができるのです。
ファクタリングは融資とは全く異なり、借入れではありません。売掛金を売買する取引に過ぎませんから、会社の負債が増える心配がなく、会社の信用情報にも影響を与えないのが大きな特徴です。この手軽さから、中小企業や個人事業主の間で資金繰りの改善策として広く活用されています。
しかし、なぜこのような取引が法的に認められているのでしょうか。その鍵を握るのが、日本の民法です。ファクタリングは、民法上の「債権譲渡」という概念に基づいて成立しているからです。
民法の規定(条文+解説)
ファクタリングの根幹をなす民法上の規定を、一つずつ見ていきましょう。参照(e-Gov法令検索)
第466条(譲渡性)
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
債権譲渡の原則と制限
民法第466条は、債権が原則として自由に譲渡できると定めています。これは、債権も財産の一つとして、自由に売買できるという考え方に基づいています。
しかし、例外も存在します。例えば、給料の差し押さえが禁止されているように、その性質上、譲渡が認められていない債権もあります。また、当事者間(取引先とあなた)で「この売掛金は他社に譲渡してはいけない」という特約(譲渡禁止特約)を結んでいる場合も、原則として譲渡できません。
この条文があるからこそ、ファクタリングという売買取引が法的に成立するのです。あなたの会社と取引先との間に発生した売掛金は、譲渡禁止特約がない限り、自由にファクタリング会社に売ることができるのです。
第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
譲渡の事実を証明するルール
ファクタリング会社が売掛金を手に入れたことを、取引先や他の人に法的に主張するためには、一定の手続きが必要です。これを「対抗要件」といいます。民法第467条は、その手続きとして以下のいずれかを求めています。
- 債務者(取引先)への通知: 「この売掛金はファクタリング会社に譲渡しましたよ」と取引先に伝えること。
- 債務者(取引先)の承諾: 取引先が「ファクタリング会社への譲渡を承諾します」と同意すること。
さらに、これらの通知や承諾は「確定日付のある証書」で行うことが求められます。確定日付とは、後から日付を改ざんできない証拠能力の高い日付のことです。たとえば、内容証明郵便や公正証書などがこれにあたります。
この規定は、ファクタリングが「2者間」と「3者間」に分かれる大きな理由となっています。3者間ファクタリングでは、ファクタリング会社がこの条文に従って、取引先への通知や承諾を必ず行います。これにより、ファクタリング会社は安心して売掛金を回収できるのです。
第468条(譲渡制限特約の効力)
(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
譲渡禁止特約の効力とその限界
先ほど述べた「譲渡禁止特約」は、ファクタリング会社が売掛金を買い取る際の大きなリスクとなります。しかし、民法第468条は、その特約の効力に一定の制限を設けています。
この条文によれば、たとえ譲渡禁止特約があったとしても、ファクタリング会社がその特約の存在を知らなかった(善意)場合は、その特約を主張できません。つまり、ファクタリング会社は特約を知らなかったことを証明できれば、売掛金を問題なく回収できるということです。
この規定は、円滑な債権の流通を保護するために設けられています。ファクタリング会社は、契約書に譲渡禁止特約がないか確認する責任がありますが、もし見落としてしまったとしても、この条文によって救済される場合があります。
第469条(二重譲渡と対抗関係)
(債権の譲渡における相殺権)
第四百六十九条 債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
3 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
まとめ(第466条〜第469条のポイント)
これまでの条文をまとめると、以下のようになります。
| 条文 | 要点 | ファクタリングへの影響 |
|---|---|---|
| 第466条 | 債権は原則自由譲渡 | ファクタリングの法的根拠 |
| 第467条 | 譲渡の対抗要件 | 3者間ファクタリングで通知・承諾が必須となる理由 |
| 第468条 | 譲渡制限特約の効力 | 特約があってもファクタリング会社が保護される場合がある |
| 第469条 | 二重譲渡の優先順位 | 確定日付のある通知・承諾の重要性 |
これらの民法規定は、ファクタリング取引における債権譲渡のルールを定め、ファクタリング会社、利用者、そして取引先それぞれの権利と義務を明確にしています。
実務での注意点(ファクタリング会社が確認すべき事項)
ファクタリング会社は、上記で述べた民法の規定を遵守するために、そして自社のリスクを最小限に抑えるために、以下のような実務的な確認を徹底します。
架空債権取引に関するリスクは以下の記事を参照してください。
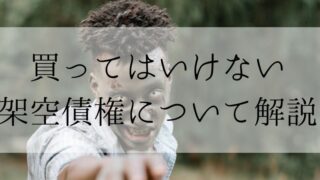
通知・承諾の有無
ファクタリング会社は、まず対象となる売掛債権が、譲渡するに足る正当なものかを厳しく審査します。特に、3者間ファクタリングの場合は、民法第467条に従い、債務者からの確定日付のある承諾、または確定日付のある通知を必ず得ます。これにより、法的に完全な形で債権を取得し、二重譲渡などの第三者に対する対抗力を確保します。
譲渡禁止特約
ファクタリング会社は、売掛金が発生した際の契約書や発注書などを詳細に確認し、譲渡を制限する特約の有無をチェックします。もし特約があった場合でも、その効力は限定的ですが、トラブルを避けるために、譲渡人に対してその事実を正確に申告するよう求めます。
二重譲渡のリスク
ファクタリング会社は、二重譲渡のリスクを極めて重大なものと捉えています。このため、契約から通知・承諾の手続きまでを最短で進めるよう努めます。特に、取引先への確定日付のある通知が、二重譲渡を防ぐ上で最も確実な方法であり、ファクタリング会社はこの手続きを厳格に行うことで、法的優位性を確立するのです。
相殺リスク
ファクタリング会社は、売掛金を買い取る前に、債務者(取引先)が譲渡人(利用者)に対して別の債務を負っていないかを慎重にヒアリングします。これにより、相殺によって回収額が減るリスクを事前に把握します。もし相殺の可能性がある場合は、その分を考慮に入れた上で、買取額を調整することがあります。
差押えリスク
ファクタリング会社は、契約を結ぶ前に、売掛金がすでに差し押さえられていないかを公的機関の情報などを通じて確認します。この調査は、民法第472条に基づくものであり、ファクタリング会社が資金を失うのを防ぐための重要なプロセスです。
債権譲渡登記制度
2者間ファクタリングでは、取引先にファクタリングの利用を知られたくないという利用者の希望に応えるため、債権譲渡登記制度を利用します。これにより、取引先への通知や承諾がなくても、法務局への登記によって法的な対抗要件を具備することが可能です。ファクタリング会社は、この制度を適切に利用することで、リスクを管理しながら利用者のニーズに応えています。
これらの確認事項は、ファクタリングが単なる「請求書買い取り」ではなく、法律に則った厳密な金融取引であることを示しています。