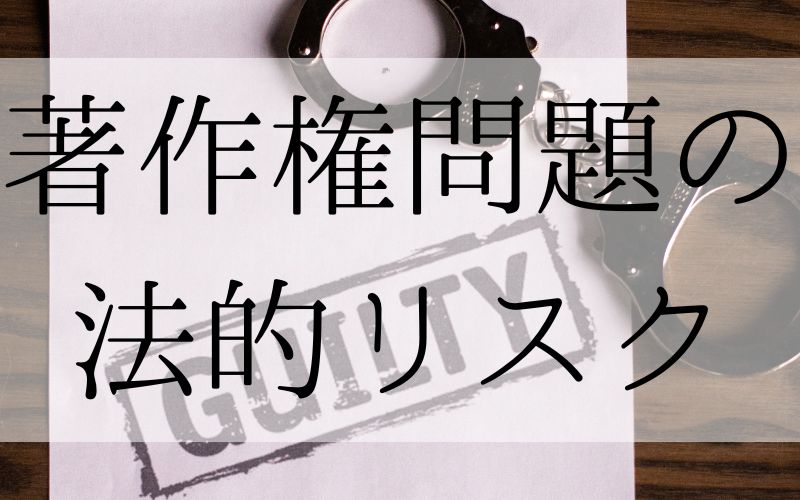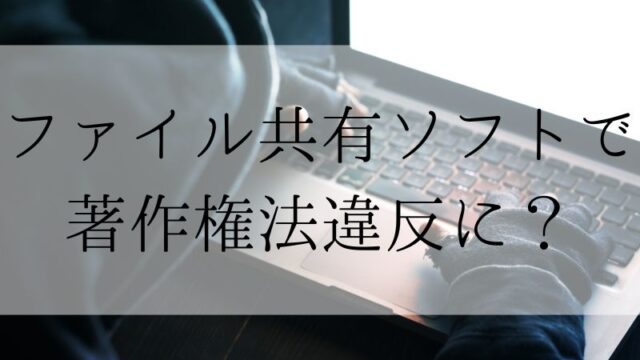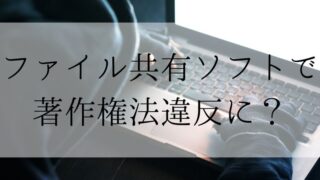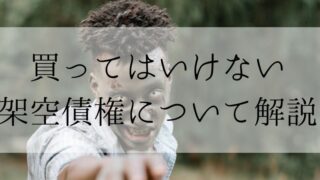「ファイル共有ソフトを使ってたら、警告メールが届いた…」「急にプロバイダから通知が来た…」
もしあなたが今、そんな不安を抱えているなら、このまま放っておくのはとても危険です。なぜなら、その通知は「著作権侵害」という犯罪行為の疑いをかけられているサインだからです。
著作権侵害は、他人が作った作品を無断で使うことで、作者(著作権者)の権利を傷つける行為です。たとえ悪気がなくても、法律違反として、高額な罰金や損害賠償を請求される可能性があります。実際に、2021年には違法ダウンロードによる被害が5,700億円以上にもなると言われています。この金額の大きさからも、問題の深刻さがわかりますね。
もし訴えられてしまうと、その対応はとても大変です。法的な知識がないまま自分で対応すると、さらに状況が悪化してしまうかもしれません。
この記事では、著作権侵害で訴えられることの法的なリスクや、弁護士に相談することがなぜ重要なのかわかりやすく紹介します。
ファイル共有ソフトはなぜ「危険」なのか?
日本のインターネット利用者における著作権侵害の認知度は依然として高い水準にあります。一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の調査によると、2021年の違法ダウンロードによる被害額は推定5,715億円に上るとされています。
では、ファイル共有ソフトによって、問われる法的な責任や、身に降りかかるかもしれない危険とはどんなものがあるのでしょうか?
著作権侵害で問われる法的責任
ファイル共有ソフトの利用が問題になるのは、著作権侵害という犯罪行為にあたるからです。ファイル共有ソフトでやり取りされるコンテンツは、ほとんどが著作権者に無断で共有されています。
著作権法では、著作者(または著作権者)に無断で著作物をアップロードする行為は「公衆送信権」の侵害として明確な違法行為です。さらに、ダウンロードする行為も、私的使用目的であっても、著作権者が許可していないものを「違法と知りながら」ダウンロードすることは違法とされています(2010年1月1日施行)。ファイル共有ソフトでやり取りされているコンテンツのほとんどが、これに該当します。
また、ファイル共有ソフトは、ダウンロードしたコンテンツが自動的にアップロードされる仕組みを持つことが多いです。ダウンロード直後にデータがアップロードフォルダにコピーされたり、ダウンロードフォルダとアップロードフォルダが同じになっている場合もあります。そのため、「ダウンロードだけしたつもり」でも、実際には無自覚に違法アップロードを行っているケースが非常に多いのです。
さらに、アップロードやダウンロードを行わなくても、ファイル共有ネットワークに参加しているだけで、ファイルの送受信の「中継点」として利用され、著作権侵害に加担させられることもあります。この点からも、安易な利用は避けるべきだと言えるでしょう。
著作権侵害に対しては、「10年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金」という非常に重い刑事罰が定められています。さらに、著作権を侵害された人(著作権者)から、損害を賠償するように求められる「民事」の責任も発生します。
著作権者に個人情報を突き止められる
ファイル共有ソフトで著作物を違法にアップロード(送信可能化)したりダウンロード(複製)したりすると、著作権法に違反し、民事・刑事の両面で責任を問われる可能性があります。
この際、著作権者が利用者を特定するためにプロバイダに送付するのが「意見照会書」です。これは、プロバイダ責任制限法第5条に基づき、著作権侵害の事実を訴える申立人が、発信者情報開示請求に先立ってプロバイダに対し、契約者の個人情報開示について意見を求める文書です。プロバイダは、この意見照会書に記載された内容(侵害行為の事実や開示の必要性など)について、契約者本人の意見を聞く必要があります。
では、この意見照会に回答をせず、無視したらどうなるのでしょうか?
その場合、プロバイダは契約者からの同意がないと判断し、発信者情報開示請求に応じる可能性が高まります。これは、プロバイダが契約者の意見を聞くという義務を果たした上で、開示の要件(侵害の明白性など)を満たしていると判断した場合、法的な手続きに従い個人情報を開示せざるを得ないためです。
たとえ意見照会書を無視したとしても、著作権者は裁判所を通じて発信者情報開示命令を申し立てることで、プロバイダに個人情報の開示を強制的に求めることができます。
結論として、意見照会書を無視しても、法的な手続きによって氏名、住所、電話番号といった個人情報が著作権者に突き止められる可能性が非常に高いです。この情報をもとに、著作権者から損害賠償請求の民事訴訟が提起されることになります。
複数の著作権者に訴えられる可能性も
ファイル共有ソフトの利用者が著作権を侵害した場合、最も重大なリスクの一つが、複数の著作権者から個別に訴訟や損害賠償請求を受ける可能性です。このリスクは、ファイル共有ソフトの特性と、著作権法の仕組みに起因します。
まず、ファイル共有ソフトで違法に流通するコンテンツは、映画、音楽、アニメ、ソフトウェアなど多岐にわたり、一つの利用者がアップロードまたはダウンロードする行為が、異なる複数の企業や個人が権利を持つ複数の著作物を侵害する可能性が非常に高いです。例えば、あるアニメシリーズをダウンロードするだけでも、そのシリーズの音楽、映像、脚本など、それぞれの著作物に対して個別の著作権者が存在し、その全ての著作権を侵害していることになります。
次に、著作権法上、著作権は個々の作品ごとにその権利者に帰属するため、一つの行為が複数の著作物の著作権を侵害した場合、各著作権者はそれぞれ独立した被害者として、損害賠償を請求する権利を持っています。これは、先の知的財産高等裁判所の判例で、原告が11人もいた事例からも明確に示されている通りです。
また、特にBitTorrentのようなP2P技術を使ったファイル共有ソフトでは、利用者がダウンロードすると同時に自動的にアップロードも行われるため、意図せずとも「送信可能化」という著作権侵害行為を継続的に行っていると見なされます。この行為は、多くの著作権者の権利を同時に侵害する「共同不法行為」と判断されることがあり、それぞれの侵害行為に対して個別の責任追及を受けることになります。
複数の著作権者が個別に損害額を請求した場合、その合計額は決して軽視できるものではありません。例えば、知的財産高等裁判所 令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)第10074号)では、8人の著作権者に対する損害賠償義務の合計額が27万円を超えていました。これは、一件当たりの損害賠償額は少額に見えても、それが複数の著作権者から請求されることで、総額が膨らむことを示しています。
これらの情報から、ファイル共有ソフトの利用は、個々の著作権者から、別々に、かつ継続的に訴訟を起こされ、最終的に高額な損害賠償を命じられるリスクがあることを明確に示しています。
実際の裁判例から見る法的問題点
「本当にそこまで厳しくなるの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、現実には多くの裁判例が存在し、その厳しさが証明されています。実際に、ファイル共有ソフトの利用者が逮捕され、有罪判決を受けた事例は数多く報告されています。
まず、逮捕・検挙された犯罪の種別ですが、著作権法違反が66%と圧倒的に多く、次いでわいせつ物陳列罪が19%、児童ポルノ禁止法違反が15%でした。このことから、特に映像系の著作権侵害ファイルが大容量なP2Pファイル共有ソフトで多く流通し、結果として取り締まりの対象になる頻度も高くなったと推測されています。
また、高名なファイル共有ソフトの問題ですと、かつて一世を風靡した「Winny」というソフトを使って著作物を違法アップロードした利用者が、懲役や罰金の刑に処されています。( 最高裁判所第三小法廷平成23年12月19日判決)
また、最近ではトレント(BitTorrent)利用者が逮捕・有罪判決を受けた事例も増えました。これは、著作権者側の特定技術が進歩し、警察の摘発がより強化されていることを意味します。
民事でも、高額な損害賠償を命じられるケースがあります。著作権者は、違法アップロードを行った利用者に対し、「本来得られるはずだった利益」などを算出し、裁判で支払いを求めるのです。中には、数百万円もの賠償金が認められたケースも存在します。
また、ファイル共有ソフトは児童ポルノ問題の温床にもなっています。警視庁の調査(2011年)によると、インターネットを利用した児童ポルノ事犯の検挙件数のうち、58.3%がファイル共有ソフトを利用した事件でした。ファイル共有ソフトの匿名性の高さが、このような違法コンテンツの拡散を助長しているのです。
実際、2010年には、警察庁の調整により21の都道府県警が連携し、ファイル共有ソフトを利用して児童ポルノを公然陳列していた被疑者18人が一斉に逮捕されました。このような大規模な摘発事例は、ファイル共有ソフトの利用が、著作権侵害だけでなく、より深刻な犯罪にもつながる可能性を明確に示しています。 参照元:警視庁「平成23年警察白書」
まとめ
ファイル共有ソフトの利用は危険? 著作権侵害で訴えられたらどうする?
「違法ダウンロード」や「著作権侵害」という言葉は聞くけれど、まさか自分が…と思っていませんか?実は、ファイル共有ソフトの安易な利用が、思いもよらない大きなリスクにつながることがあります。
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によると、2021年の違法ダウンロードによる被害額は推定5,715億円。これは社会全体の問題であり、決して他人事ではありません。
ファイル共有ソフトでコンテンツをやり取りすると、著作権法違反として、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という厳しい刑事罰の対象となる可能性があります。さらに、著作権者からは損害賠償を求められる民事責任も発生します。
「ダウンロードしただけなのに…」と思うかもしれません。しかし、多くのファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードが行われる仕組み(送信可能化)になっています。そのため、意図せず違法アップロードに加担し、複数の著作権者から個別に訴えられるリスクも潜んでいます。
著作権侵害で訴えられそうになったら、すぐに弁護士へ相談!
「プロバイダから意見照会書が届いた」「警告メールが来た」など、著作権侵害の疑いで通知が届いたら、一人で悩まず、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士は、あなたの状況を正確に分析し、警察の捜査対応や著作権者との示談交渉を代行します。これにより、刑事事件化や高額な賠償請求を回避し、問題の早期解決を目指すことができます。
著作権問題は専門性が高く、個人での対応は非常に困難です。相談無料の事務所や、IT・著作権法に詳しい弁護士に依頼することで、不安を解消し、適切な法的サポートを受けられます。
ご自身の未来を守るためにも、まずは専門家にご相談ください。